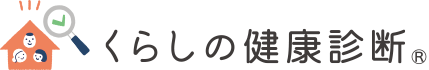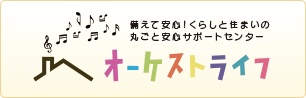くらしの健康診断
2025年11月12日 [くらしの健康診断]
その相続ちょっと待った!〜不動産相続

みなさん、こんにちは!
司法書士の清水です。
当所では、これまでの20年以上の不動産に関する経験により、不動産の個々人間売買や相続された不動産(特に遠隔地にある不動産)の売却や有効活用方法についてアドバイスさせていただく機会が増えています。
専門家の立場として、当所が主宰している士業グループ「LTR」のメンバーである税理士、不動産鑑定士、不動産コンサルタントからも意見をもらいながら、お客様の判断材料にしていただくために必要な情報(メリット・デメリットやリスク)を客観的かつ総合的にお伝えできるようにしています。
ここでは例として、不動産相続の相談ケースを取り上げます。
不動産を相続することは、多くの人にとって大きな出来事です。
しかし、最近では「不動産神話が崩壊している」とも言われており、相続に伴うリスクやデメリットが増しています。
特に、好立地や開発が進むエリアの不動産は、将来的に価値が上がる可能性があります。
特に、需要のあるエリアであれば、長期的な収入を見込むことができます。
また、特定の条件を満たすことで、小規模宅地等の特例が適用され、さらなる税負担軽減が可能です。
利用価値が低く、売却も難しい不動産を相続してしまうと所有するだけで負担になる不動産、いわゆる「負動産」となり、ただ維持費用だけがかかる状態になってしまうことがあります。
特に、地方の不動産や利用価値の低い物件は、相続時の価値と比べて売却時に大幅に価値が下がることがあります。
特に何世代もの前の所有者が亡くなったまま相続登記がされていない場合、相続人の数が増えて権利関係が複雑になってしまっているケースが多いです。
※2024年4月1日から相続登記が義務化されましたが、施行日前の過去の相続分も義務化の対象となります。
主として3つの観点から見極めていきましょう。
以上のように不動産相続には、多くのメリットと同時に、デメリットやリスクも存在します。
相続するかどうかを検討するためには、資産価値を知り、さらに将来、起こりうるリスクを把握したうえで、相続予定の不動産を客観的に評価することが大切です。
当所では、士業グループ「LTR」のメンバーである税理士、不動産鑑定士、不動産コンサルタントなどと密な連携をとっており、司法書士だけでは対応できない問題もワンストップで解決できるようにしています。
お気軽にご相談いただけますと幸いです。
司法書士の清水です。
当所では、これまでの20年以上の不動産に関する経験により、不動産の個々人間売買や相続された不動産(特に遠隔地にある不動産)の売却や有効活用方法についてアドバイスさせていただく機会が増えています。
専門家の立場として、当所が主宰している士業グループ「LTR」のメンバーである税理士、不動産鑑定士、不動産コンサルタントからも意見をもらいながら、お客様の判断材料にしていただくために必要な情報(メリット・デメリットやリスク)を客観的かつ総合的にお伝えできるようにしています。
ここでは例として、不動産相続の相談ケースを取り上げます。
不動産を相続することは、多くの人にとって大きな出来事です。
しかし、最近では「不動産神話が崩壊している」とも言われており、相続に伴うリスクやデメリットが増しています。
不動産相続のメリットは?
資産としての価値
不動産は預貯金、株式などの金融資産とは異なり、実物資産としての安定性があります。特に、好立地や開発が進むエリアの不動産は、将来的に価値が上がる可能性があります。
賃貸収入
相続した不動産を賃貸に出すことで、安定した収入源となる可能性があります。特に、需要のあるエリアであれば、長期的な収入を見込むことができます。
節税対策
不動産は相続税の計算上、預金や現金よりも評価額が低くなる場合があり、節税効果が期待できることがあります。また、特定の条件を満たすことで、小規模宅地等の特例が適用され、さらなる税負担軽減が可能です。
不動産相続のデメリットは?
維持費用がかかる
固定資産税や管理費、修繕費などの維持費用がかかり、所有している以上は支払わなければならないため、経済的な負担が発生します。利用価値が低く、売却も難しい不動産を相続してしまうと所有するだけで負担になる不動産、いわゆる「負動産」となり、ただ維持費用だけがかかる状態になってしまうことがあります。
売却時の費用
不動産を売却する際には測量代、仲介手数料や譲渡所得税などの費用がかかるため、資産価値が低い不動産の場合は売却後に手元に残る金額が少なくなることがあります。共有名義の問題
複数の相続人同士の共有名義で相続した場合、活用方法について意見の相違が発生しやすくなります。例えば、売却に賛成、反対など意見が分かれることで活用が進まないことも多いです。不動産価値の下落
経済状況や人口減少により、不動産価値が下落するリスクが高まっています。特に、地方の不動産や利用価値の低い物件は、相続時の価値と比べて売却時に大幅に価値が下がることがあります。
権利関係の複雑化
更なる相続の発生によって、不動産の権利関係が複雑化することがあります。特に何世代もの前の所有者が亡くなったまま相続登記がされていない場合、相続人の数が増えて権利関係が複雑になってしまっているケースが多いです。
※2024年4月1日から相続登記が義務化されましたが、施行日前の過去の相続分も義務化の対象となります。
不動産を相続するかどうかを見極めるポイントは?
主として3つの観点から見極めていきましょう。
周辺地域の人口・世帯、」災害指定区域、地域の特性などに関する情報を把握
どのくらいの入居者数が見込めるのか、どのような世帯の需要があるのかが把握できます。さらに将来の見通しを考えつつ、定期見直しも必要となります。収益性・資産性一次チェック
このまま所有し続けるのか、資産の組み替えをした方がいいのかなどの判断材料になります。さらに将来の見通しを考えつつ、定期見直しも必要となります。税務一次チェック
所得税と相続税のバランスをチェックします。さらに将来の見通しを考えつつ、定期見直しも必要となります。以上のように不動産相続には、多くのメリットと同時に、デメリットやリスクも存在します。
相続するかどうかを検討するためには、資産価値を知り、さらに将来、起こりうるリスクを把握したうえで、相続予定の不動産を客観的に評価することが大切です。
当所では、士業グループ「LTR」のメンバーである税理士、不動産鑑定士、不動産コンサルタントなどと密な連携をとっており、司法書士だけでは対応できない問題もワンストップで解決できるようにしています。
お気軽にご相談いただけますと幸いです。