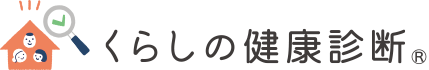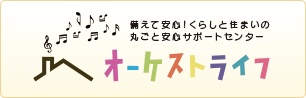くらしの健康診断
2025年10月08日 [くらしの健康診断]
想いを未来へ託す 遺贈とは

みなさん、こんにちは!
司法書士の清水です。
この4月から横浜市社会福祉協議会「福祉分野への遺贈(寄付)に関する専門相談」の助言者として活動しています。
福祉分野への遺贈を検討している方々に向けた無料の相談窓口であり、弁護士や司法書士などの法律の専門家が遺言書の作成や遺贈手続きについてアドバイスするものです。
当所でもこれまで遺言作成とあわせて遺贈について質問をいただくことがありました。よく質問があることを下記にまとめてみます。
「遺贈」
遺言によって行われる財産の譲渡です。
遺言を残した人が亡くなった後に効力が発生しますので、死後に行うものです。
遺贈を受ける人(受遺者)あらかじめ指定しておくことで、遺言執行者(遺言に書かれた内容に従って故人の遺志を実行する責任を負う人)が遺言を残した人の死後に代わりに手続きを行います。
「寄付」
意味:生前に財産を他人または団体に譲渡するものです。
寄付は、契約に基づいて即時に効力が発生しますから、お元気なうちに自分の意思で行うことができます。
遺贈を実行するには、遺言書を作成することが前提となります。
法的な効力を持たせるために、定められた方式に則って作成しないといけません。
◆誤解やトラブルにつながらない内容を考慮
遺言書にはどの財産を誰に渡すかを具体的に記載する必要があります。
相続人に誤解を与えたり、あらぬトラブルを招くことのないように、例えば、どうして遺贈したいのか理由、想いや気持ちは「付言事項」でしたためましょう。
◆税務上も考慮
遺贈には税金が伴う場合があります。相続税の影響を受ける可能性があるため、遺贈を行う前に専門家に相談しておきましょう。
◆遺贈先候補の綿密な調査が必要
信頼のおける遺贈先なのか、遺贈したものの使途の透明性は担保されているのか綿密な調査が必要です。
活動実績や評判など信頼のできる根拠となるような情報を探します。お亡くなりになった時点で存在していないような脆弱な基盤の団体は選ばないように気をつけましょう。
また、団体によっては不動産の現物遺贈は全てお断りとしている場合もありますので、どのような遺贈が可能なのか前もって検討する必要があります。
◆遺言執行者を指名しておく
遺言に書かれた内容に従って故人の遺志を確実に実行してもらえるように遺言執行者を決めて遺言書に記載しておくようにしましょう。
日本国内で年間どれくらいの遺贈が行われているか正式な統計調査がないので肌感覚でしかありませんが、認知度が低いせいなのか、まだまだ相談件数自体は少ない状況です。
ただ、少ないながらも「自分の財産を未来につなげたい、社会のために役立ててほしい」という強い思いをもっている方もいらっしゃいます。
進行性の病気で余命いくばくもない方の病床に呼ばれて「エンジニアとして手に職を得ることができた。その礎となった母校の県立高校に遺贈したい」とご依頼をいただいたことがあります。
自分の人生を振り返ったときに誰かの役に立ちたい、今、ここに自分がいるのもあの時、あの高校に入学できたことが始まりだったと思い立ったそうです。
県立高校のある地域の県庁の所管課に取り急ぎ、遺贈の方法を確認し、ご本人に流れを説明したところ「これで自分の想いが形にできる」と大変悦ばれ、その数日後に安心したかのように息を引き取られたことが印象的でした。
この方のように遺贈先が明確な方たちばかりではありません。
想いさえあれば、遺贈は可能です。当所ではそれを形にするためのサポートをすることができます。
当所ではご自身の価値観に合う遺贈先探しからお手伝いしています。
例えば、犬に関連する団体が良いという方がいました。いろいろお話をしている中で、盲導犬や聴導犬として人間に尽くしてきた犬たちが老後を過ごす施設の運営をしている団体が良いという考えにゆきつかれました。
その考えを受け、当所では団体の信頼性や遺贈した先の使途の透明性などを綿密に調査した上で、その方の遺言書の中に遺贈先として記載いたしました。
当所では遺贈に関心があるけれど何から始めていいかわからない、流れがしりたいなど、皆さんが少しでも遺贈を身近に感じていただけるようなご相談をお受けしておりますので、お気軽にご連絡ください。
司法書士の清水です。
この4月から横浜市社会福祉協議会「福祉分野への遺贈(寄付)に関する専門相談」の助言者として活動しています。
福祉分野への遺贈を検討している方々に向けた無料の相談窓口であり、弁護士や司法書士などの法律の専門家が遺言書の作成や遺贈手続きについてアドバイスするものです。
当所でもこれまで遺言作成とあわせて遺贈について質問をいただくことがありました。よく質問があることを下記にまとめてみます。
遺贈と寄付の違いは?
遺贈、寄付どちらとも財産を他人に譲渡する行為ですが、下記の違いがあります。「遺贈」
遺言によって行われる財産の譲渡です。
遺言を残した人が亡くなった後に効力が発生しますので、死後に行うものです。
遺贈を受ける人(受遺者)あらかじめ指定しておくことで、遺言執行者(遺言に書かれた内容に従って故人の遺志を実行する責任を負う人)が遺言を残した人の死後に代わりに手続きを行います。
「寄付」
意味:生前に財産を他人または団体に譲渡するものです。
寄付は、契約に基づいて即時に効力が発生しますから、お元気なうちに自分の意思で行うことができます。
遺贈を行う際の注意点は?
◆法的要件を満たした遺言書の作成が前提遺贈を実行するには、遺言書を作成することが前提となります。
法的な効力を持たせるために、定められた方式に則って作成しないといけません。
◆誤解やトラブルにつながらない内容を考慮
遺言書にはどの財産を誰に渡すかを具体的に記載する必要があります。
相続人に誤解を与えたり、あらぬトラブルを招くことのないように、例えば、どうして遺贈したいのか理由、想いや気持ちは「付言事項」でしたためましょう。
◆税務上も考慮
遺贈には税金が伴う場合があります。相続税の影響を受ける可能性があるため、遺贈を行う前に専門家に相談しておきましょう。
◆遺贈先候補の綿密な調査が必要
信頼のおける遺贈先なのか、遺贈したものの使途の透明性は担保されているのか綿密な調査が必要です。
活動実績や評判など信頼のできる根拠となるような情報を探します。お亡くなりになった時点で存在していないような脆弱な基盤の団体は選ばないように気をつけましょう。
また、団体によっては不動産の現物遺贈は全てお断りとしている場合もありますので、どのような遺贈が可能なのか前もって検討する必要があります。
◆遺言執行者を指名しておく
遺言に書かれた内容に従って故人の遺志を確実に実行してもらえるように遺言執行者を決めて遺言書に記載しておくようにしましょう。
遺贈を検討される皆さんへ
当所では遺言書の作成〜遺言執行者の受任まで幅広く担当しております。日本国内で年間どれくらいの遺贈が行われているか正式な統計調査がないので肌感覚でしかありませんが、認知度が低いせいなのか、まだまだ相談件数自体は少ない状況です。
ただ、少ないながらも「自分の財産を未来につなげたい、社会のために役立ててほしい」という強い思いをもっている方もいらっしゃいます。
進行性の病気で余命いくばくもない方の病床に呼ばれて「エンジニアとして手に職を得ることができた。その礎となった母校の県立高校に遺贈したい」とご依頼をいただいたことがあります。
自分の人生を振り返ったときに誰かの役に立ちたい、今、ここに自分がいるのもあの時、あの高校に入学できたことが始まりだったと思い立ったそうです。
県立高校のある地域の県庁の所管課に取り急ぎ、遺贈の方法を確認し、ご本人に流れを説明したところ「これで自分の想いが形にできる」と大変悦ばれ、その数日後に安心したかのように息を引き取られたことが印象的でした。
この方のように遺贈先が明確な方たちばかりではありません。
想いさえあれば、遺贈は可能です。当所ではそれを形にするためのサポートをすることができます。
当所ではご自身の価値観に合う遺贈先探しからお手伝いしています。
例えば、犬に関連する団体が良いという方がいました。いろいろお話をしている中で、盲導犬や聴導犬として人間に尽くしてきた犬たちが老後を過ごす施設の運営をしている団体が良いという考えにゆきつかれました。
その考えを受け、当所では団体の信頼性や遺贈した先の使途の透明性などを綿密に調査した上で、その方の遺言書の中に遺贈先として記載いたしました。
当所では遺贈に関心があるけれど何から始めていいかわからない、流れがしりたいなど、皆さんが少しでも遺贈を身近に感じていただけるようなご相談をお受けしておりますので、お気軽にご連絡ください。