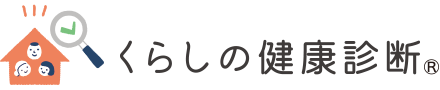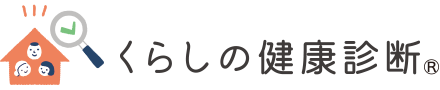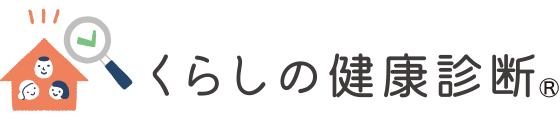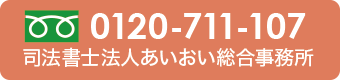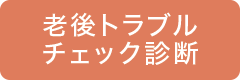くらしの健康診断
2025年07月07日 [くらしの健康診断]
家族信託は誰に向いている? 〜制度の特徴と活用のコツをわかりやすく解説〜

みなさん、こんにちは。司法書士の清水です。
最近、「家族信託(民事信託)」という言葉を耳にすることが増えてきたのではないでしょうか?
「親の財産管理がしやすくなる」「相続対策になる」「認知症対策にも使える」などと紹介され、関心を持つ方が多いです。
実際に私の事務所でもここ数年、家族信託に関するご相談が増えています。
一方で、お話を詳しく伺うと次のようなケースがとても多いのも現実です。
・子の利益が優先されている(親の意向が十分に確認されていない)
・親がすでに認知症で契約自体が結べない
・財産状況から見て家族信託が不要または不適切
家族信託は 正しく使えば非常に有用な制度 ですが、誰にでも必要なものではありません。
また、設計を誤ると 家族間トラブルや税務リスク を生むこともあります。
今回は家族信託が適しているケース/不要なケース/注意すべきポイント を、わかりやすく整理してご紹介します。
ぜひ、ご家庭で導入を検討する際の参考にしてください。
① 不動産の管理・活用を考えている場合
不動産は管理や活用に柔軟性が求められる資産です。
親の高齢化や体調変化を見据えて、子などがスムーズに管理・活用できる体制を作っておくには家族信託がとても有効です。
【具体例】
遠方にある 賃貸アパート → 将来、親が管理困難になる前に、子が修繕や賃貸契約更新、売却などを行えるように準備しておく。
空き家になる予定の実家 → 将来的な売却や賃貸に備えて、子に不動産の管理・処分の権限を託しておく。
親が認知症になると不動産の売却や契約は非常に困難になります。
事前に家族信託で備えておけば、家族が柔軟に対応できます。
② 将来の財産整理や家族トラブルを防ぎたいとき
「親が元気なうちに将来のことをきちんと整理しておきたい」
「相続でもめるのは避けたい」
そんな思いから家族信託を活用するご家庭も増えています。
【具体例】
施設入居や医療費に備えて 親名義の家や土地を売却して費用に充てたい。将来親が判断できなくなっても、子が手続きを進められるように準備する。
相続の時に 兄弟間で不動産の分け方をめぐって揉めそう → 信託契約で、売却や分配の流れ・管理者を事前に明確に定め、トラブル防止につなげる。
家族信託を使えば、売却や分配のルール・手順をあらかじめ契約で定められるため、相続時に「誰がどう動くべきか」が明確になります。
結果として、家族全員の安心につながります。
③ 親の会社やお店の財産をスムーズに引き継ぎたいとき
親が会社やお店、事業用の土地や建物を持っている場合、将来の承継準備として家族信託はとても役立ちます。
事業や店舗は「止めたくない」「家族で守りたい」と思っていても、親が急な病気や認知症になると手続きが止まり、取引先や従業員に迷惑がかかるケースが多いのです。
【具体例】
親が経営している会社の株式(議決権) → 子に信託し、子が経営判断をスムーズに行えるように準備する。親は利益だけ受け取る仕組みに。
店舗用地や建物 → 子が賃貸契約や修繕、建て替えなどの判断・実行を行えるよう事前に権限を持たせておく。
家族信託を使えば、事業やお店がスムーズに続けられる体制 を整えることができます。
親が元気な間は現状のまま、将来のリスクに備えておく柔軟な仕組みとして有効です。
④ 家族に障がい者や支援が必要な方がいる場合
親亡き後の不安が大きいご家庭では、家族信託によって継続的な財産管理・生活支援が可能になります。
【具体例】
障がいのある子 → 親の財産を信託し、生活費や医療費などを定期的に支出できる体制を整える。
高齢の配偶者や支援が必要な家族 → 信託契約により、生活費の支払い方法や管理手順を明確にしておくことで、生活の質と安心を守る。
家族信託は 生活の安定と安心を支える強力な仕組みとなります。
親亡き後の生活を支える道筋を整えておけることは、家族にとって大きな安心材料となります。
① 財産が預貯金と自宅のみの場合
親の財産が 預金+自宅のみ の場合は、家族信託が必ずしも必要ではありません。
【対応例】
預金 → 銀行の代理人届けやキャッシュカード管理で十分対応可能。
自宅 → 遺言や遺産分割協議 により適切に承継できる。
信託の設計や維持にかかるコストや手間を考えると、もっと簡単な方法で十分な場合が多いです。
② 親がすでに認知症で判断能力がない場合
家族信託は契約行為なので、親本人の意思確認が必須です。
すでに認知症が進行し意思能力が不十分な場合、信託契約は締結できません。
この場合は、成年後見制度 の活用が現実的な選択肢となります。
③ 子の利益を優先した設計になっている場合
親の意向より子の資産形成を目的として信託が組まれている。信託財産が親の利益にならず、親の生活や権利が損なわれてしまう。
こうした不適切な設計 は、将来的に 家族間トラブルや税務問題 の原因になります。
親本人の利益保護を第一に据える ことが大前提です。
当事務所では司法書士業務に加え、弁護士・税理士・不動産鑑定士・土地家屋調査士・社会保険労務士・建築士 などの士業ネットワーク「LTRコンサルティングパートナーズ」及び不動産会社・リフォーム業者・片付け業者・防犯業者 など実務に強い「オーケストライフ」を主宰し、密接に連携しています。
家族信託をご検討の際には必要に応じたチーム型支援体制により、ご家族にとって 本当に安心で適切な信託設計をサポートいたします。
弁護士 → 法的な契約内容のチェック/トラブル防止
税理士 → 税務リスク確認/最適な節税提案
不動産専門家 → 財産評価/資産活用のアドバイス
不動産管理業者→ 不動産の維持管理や活用提案
家族信託はとても魅力的な制度ですが、すべての家庭に必要なものではありません。
「本当に制度を使うべきか」「他の制度で代替できないか」「家族の状況に合った適切な設計になっているか」
これらを冷静に見極めることが大切です。
もし迷った場合は、ぜひご相談ください。
制度そのものの正しい使い方はもちろん、ご家族の思いに寄り添った 最適な解決策をご提案いたします。
最近、「家族信託(民事信託)」という言葉を耳にすることが増えてきたのではないでしょうか?
「親の財産管理がしやすくなる」「相続対策になる」「認知症対策にも使える」などと紹介され、関心を持つ方が多いです。
実際に私の事務所でもここ数年、家族信託に関するご相談が増えています。
一方で、お話を詳しく伺うと次のようなケースがとても多いのも現実です。
・子の利益が優先されている(親の意向が十分に確認されていない)
・親がすでに認知症で契約自体が結べない
・財産状況から見て家族信託が不要または不適切
家族信託は 正しく使えば非常に有用な制度 ですが、誰にでも必要なものではありません。
また、設計を誤ると 家族間トラブルや税務リスク を生むこともあります。
今回は家族信託が適しているケース/不要なケース/注意すべきポイント を、わかりやすく整理してご紹介します。
ぜひ、ご家庭で導入を検討する際の参考にしてください。
家族信託が適しているケース
① 不動産の管理・活用を考えている場合
不動産は管理や活用に柔軟性が求められる資産です。
親の高齢化や体調変化を見据えて、子などがスムーズに管理・活用できる体制を作っておくには家族信託がとても有効です。
【具体例】
遠方にある 賃貸アパート → 将来、親が管理困難になる前に、子が修繕や賃貸契約更新、売却などを行えるように準備しておく。
空き家になる予定の実家 → 将来的な売却や賃貸に備えて、子に不動産の管理・処分の権限を託しておく。
親が認知症になると不動産の売却や契約は非常に困難になります。
事前に家族信託で備えておけば、家族が柔軟に対応できます。
② 将来の財産整理や家族トラブルを防ぎたいとき
「親が元気なうちに将来のことをきちんと整理しておきたい」
「相続でもめるのは避けたい」
そんな思いから家族信託を活用するご家庭も増えています。
【具体例】
施設入居や医療費に備えて 親名義の家や土地を売却して費用に充てたい。将来親が判断できなくなっても、子が手続きを進められるように準備する。
相続の時に 兄弟間で不動産の分け方をめぐって揉めそう → 信託契約で、売却や分配の流れ・管理者を事前に明確に定め、トラブル防止につなげる。
家族信託を使えば、売却や分配のルール・手順をあらかじめ契約で定められるため、相続時に「誰がどう動くべきか」が明確になります。
結果として、家族全員の安心につながります。
③ 親の会社やお店の財産をスムーズに引き継ぎたいとき
親が会社やお店、事業用の土地や建物を持っている場合、将来の承継準備として家族信託はとても役立ちます。
事業や店舗は「止めたくない」「家族で守りたい」と思っていても、親が急な病気や認知症になると手続きが止まり、取引先や従業員に迷惑がかかるケースが多いのです。
【具体例】
親が経営している会社の株式(議決権) → 子に信託し、子が経営判断をスムーズに行えるように準備する。親は利益だけ受け取る仕組みに。
店舗用地や建物 → 子が賃貸契約や修繕、建て替えなどの判断・実行を行えるよう事前に権限を持たせておく。
家族信託を使えば、事業やお店がスムーズに続けられる体制 を整えることができます。
親が元気な間は現状のまま、将来のリスクに備えておく柔軟な仕組みとして有効です。
④ 家族に障がい者や支援が必要な方がいる場合
親亡き後の不安が大きいご家庭では、家族信託によって継続的な財産管理・生活支援が可能になります。
【具体例】
障がいのある子 → 親の財産を信託し、生活費や医療費などを定期的に支出できる体制を整える。
高齢の配偶者や支援が必要な家族 → 信託契約により、生活費の支払い方法や管理手順を明確にしておくことで、生活の質と安心を守る。
家族信託は 生活の安定と安心を支える強力な仕組みとなります。
親亡き後の生活を支える道筋を整えておけることは、家族にとって大きな安心材料となります。
家族信託が不要なケース
① 財産が預貯金と自宅のみの場合
親の財産が 預金+自宅のみ の場合は、家族信託が必ずしも必要ではありません。
【対応例】
預金 → 銀行の代理人届けやキャッシュカード管理で十分対応可能。
自宅 → 遺言や遺産分割協議 により適切に承継できる。
信託の設計や維持にかかるコストや手間を考えると、もっと簡単な方法で十分な場合が多いです。
② 親がすでに認知症で判断能力がない場合
家族信託は契約行為なので、親本人の意思確認が必須です。
すでに認知症が進行し意思能力が不十分な場合、信託契約は締結できません。
この場合は、成年後見制度 の活用が現実的な選択肢となります。
③ 子の利益を優先した設計になっている場合
親の意向より子の資産形成を目的として信託が組まれている。信託財産が親の利益にならず、親の生活や権利が損なわれてしまう。
こうした不適切な設計 は、将来的に 家族間トラブルや税務問題 の原因になります。
親本人の利益保護を第一に据える ことが大前提です。
士業ネットワークを活かした安心サポート体制
当事務所では司法書士業務に加え、弁護士・税理士・不動産鑑定士・土地家屋調査士・社会保険労務士・建築士 などの士業ネットワーク「LTRコンサルティングパートナーズ」及び不動産会社・リフォーム業者・片付け業者・防犯業者 など実務に強い「オーケストライフ」を主宰し、密接に連携しています。
家族信託をご検討の際には必要に応じたチーム型支援体制により、ご家族にとって 本当に安心で適切な信託設計をサポートいたします。
弁護士 → 法的な契約内容のチェック/トラブル防止
税理士 → 税務リスク確認/最適な節税提案
不動産専門家 → 財産評価/資産活用のアドバイス
不動産管理業者→ 不動産の維持管理や活用提案
家族信託はとても魅力的な制度ですが、すべての家庭に必要なものではありません。
「本当に制度を使うべきか」「他の制度で代替できないか」「家族の状況に合った適切な設計になっているか」
これらを冷静に見極めることが大切です。
もし迷った場合は、ぜひご相談ください。
制度そのものの正しい使い方はもちろん、ご家族の思いに寄り添った 最適な解決策をご提案いたします。